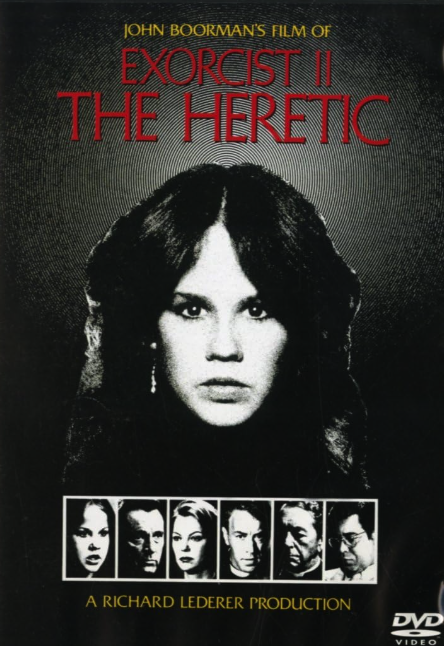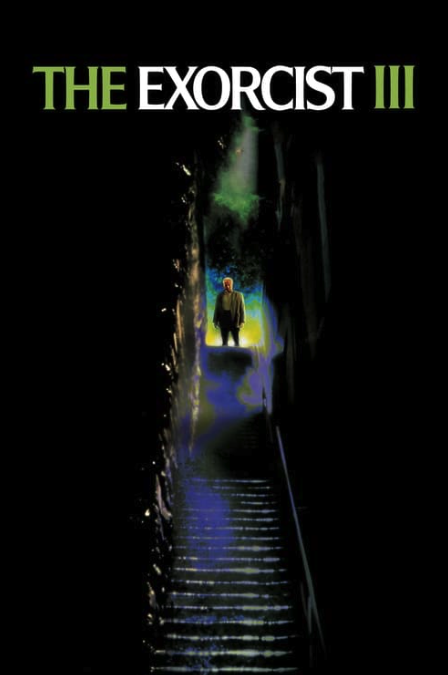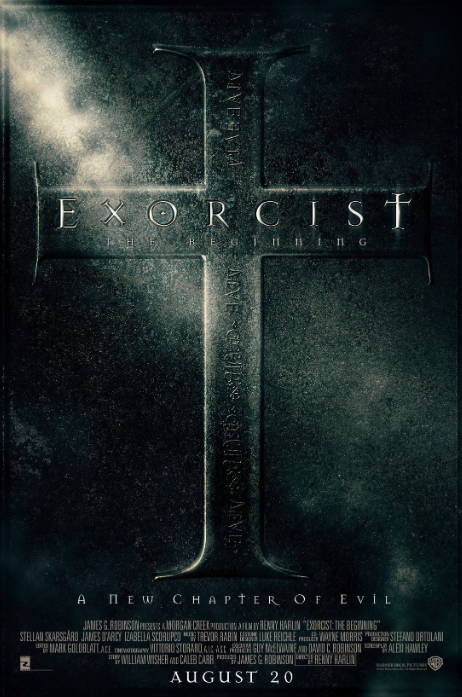しばらくスニーカーの記事を書いてなかった間に、どうやらNIKEバブルが崩壊し、二次流通価格もいっときの盛り上がりを失って、ファッション中心地からはサロモンがネクストトレンドとしての機運が高まり、レディーススニーカー市場では今でも厚底が有り難がられている。勘のいい観測者はあのNIKE KOKO SANDALがどうやらいろんなところに売っていて、そのへんのスーパーに寄ってもKOKO SANDALを得意げに履いたお母さんを目撃できる、という事実で時代の移り変わりが読み取れるのである。先日Instagramで友人の投稿に全身が痒くなるような気になった。自信満々に抽選ゲットしたDUNKを『プレネあがるぞ!』と投稿している友人である。検索してみると上代1.8万のそいつはやっぱりメルカリに大量に溢れていて、2万程度でごろごろ転がっている。残念ながらほぼ売れずにニ次流通の海を漂い彷徨っている状態には、もはやNIKEはステータスにもマウントにもならなくなっている事実を改めて再確認させられた。new balanceも、NIKEに遅れながらスニーカーバブルの波に乗れたところで、バイヤーたちはそっぽを向いていて、マス層にとっては目を覆いたくなるような自信の値段は受け入れられない。やはりスニーカーバブル期はどこか病んでたのではないかとさえ思う。Aimé Leon Doreによって再発掘された550は、円安がどこまで関係あるかはわからないが、上代を2万円近くまであげていて現在では40%OFFもザラに見られる状況だ。この状況にはテディ・サンティスもレーニア片手に泣いている。冒頭の通り、ファッション感度の高い人達は『サロモン』『ホカ』『オン』に流れて秋を迎えると思えたが、こういったトレイル・ハイパフォーマンス系のトレンドは長らく続いたスニーカーブーム最後の灯火となりそうだ。
パリミラノの2024FWコレクションを見ても明らかなように、クラシック・グランパ・カウボーイ・オフィスコアといった提案で埋め尽くされている。長らく続いたストリートスタイルへのカウンタートレンドである。というか、トレンドは人と違うからおしゃれなのである。ワイドフィット、オーバーサイズ、クルーT、ユニクロワイドタックパンツ、Y2K、ヘビーウェイトなパーカー、DUNK、サンバ。どこを見ても同じような場所で買った同じようなものを着る人たち。何度言われても、やっぱりそうだなぁ、と思うように時代は回るのである。バブアーやマッキントッシュは数年前から熱を浴びていて、今からアイコン化はしないと思うが、こういった普遍的で伝統的で保守的、いわゆるトラッドなものがトレンドになる流れはどのブランドからも感じる。カウボーイ的なアイテムは時代にフィットしているワイドなサイズ感を演出し、オフィスコア、つまりジャケットやセットアップを再定義しようとしている。この冬は、オーバーサイジングされ、くびれのないテーラードジャケットを着たおしゃれ女子が見られるはずだ。足元はどうなるのかという話だが、革靴である。ユニクロが出しているチャンキーソールのローファーのような、スニーカーと革靴のグラデーションを狙ったアイテムがマス層に供給されると思うが、ファッション感度の高いメンズたちは、それこそトラッドなものに金をかけるはずである。パラブーツ、オールデン、チャーチ、ジャランスリワヤ、GHバスあたりが手を出しやすく、古着屋でJMウェストン、ジョンロブ、グッチ探す。結局、オンラインでどんなブランドでも手に入る現在へのカウンターカルチャー的な構図にある古着屋ブームの再来が、こういった次のトレンドとマッチしまくるのである。これではアニキもツボウォークも波に乗れるわけで、今からヨダレを垂らしているはず。似たようなことするYouTuberが割と出てきているのもおもろい。そんなことを考えると、スニーカーブームの終焉は当然に思える。ここから先はハイプスニーカー二次流通で店を出しているところはかなり厳しいだろうし、ファッショントレンド向けのスニーカー小売もきつい。アトモスを売るタイミングは完璧だった。
それにしても不景気である。税金、円安、物価高みたいな文字が岩みたいなフォントでマイライフマイゲームに立ちはだかり、南海トラフ臨時情報とか災害も日常化。そりゃ、スケッチャーズが売れる。いまから15年前、ファッションとは別軸でマスに大ウケしたシェイプアップシューズというカテゴリーがある。火付け役はスケッチャーズのシェイプアップス、後追いでリーボックのイージートーン、new balanceもトゥルーバランスと言ったプライドの無いネーミングで参入し、全世界で5000億円ほどの市場となった。履くだけで痩せる、シェイプアップできる、などの謳い文句で日本でも飛ぶように売れたわけだが、起訴大国アメリカで「痩せないやんか!」とリーボックが訴訟され、日本では東日本大震災でそんな場合じゃなくなってこの市場は消滅した。でもあの一般ユーザー(ファッションとは別という意味で)の熱狂はすごかった。それと同じような現象が今、すでに起きている。スケッチャーズのスリップインズである。 かがまず手を使わずに脱ぎ履きできる謳い文句で中年層〜高齢者が大体の構成比を占めていると思うが、AIR FORCE1までイージーインなんつって使っているので頭をかかえたりした。人々が求めているのは機能美では無い。“機能”である。結局、時代背景が消費傾向を左右する。想像できるだろう、自社開発したりOEMだったりでスニーカーと革靴の中間みたいな靴を7000円〜2万くらいで展開し、ハンズフリー系シューズを年配層が買う。アトモスみたいなスニーカーセレクトは衰退して古着屋が増えていく。高円寺のウィスラー/チャートは注目を浴びるだろうし、アウトレットにはJMウェストンやクラークスがさらに展開を増やす。リーガルはなんとかそれっぽい靴を作るが販売チャンネルが少なくて頓挫、MADE IN JAPANを貫くハルタはファッションカテゴリーでブレイクしたい。今後はスニーカーよりも革靴の話が多くなりそうだ。どちらかといえばこっちのほうが専門なので言いたいことが山ほどある。
そうそう、予告したいのは革靴トレンドがもし行き詰まったら、コンバースがくる。某商社のJAPANコンバースが一昨年くらいからやりはじめたUSシリーズはすごく良い。